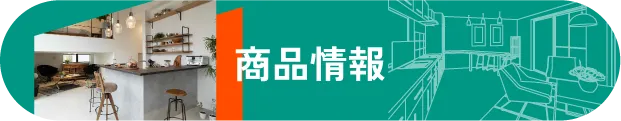「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。

「ロフトのある家」に憧れを抱く方は多いのではないでしょうか。ロフトは、限られた空間を有効活用できる魅力的なスペースとして注目される一方で、「建ててから後悔した」という声も聞かれます。
この記事では、ロフトの定義、メリット、デメリットに加えて、後悔しないためのポイントをご紹介します。
ロフトとは?その定義と特徴
ロフトの正確な定義や、どんな特徴があるのかご存知でしょうか?
ロフトとは、部屋の天井を高くしてつくられた二層式の空間のうち、上の層を指します。建築基準法では「小屋裏物置等」として扱われ、居室とは見なされないため、税負担を軽減できるという特徴があります。
ただし、ロフトには以下の法的制約があります。
【天井高の制限】
原則として1.4m以下と定められています。そのため、立って作業するには不向きな場合が多いです。また、ロフトの下の空間の天井高は2.1mと定められています 。
【床面積の制限】
ロフトにアクセスする階の床面積の2分の1未満に抑える必要があります 。
これらの制限を超える場合、居室とみなされ、延床面積や容積率に算入されてしまいます。
ロフトのある家のデメリットと対策
ロフトのデメリットとその対策を事前に知り、後悔のないロフト計画を立てましょう。
温度管理が難しい
ロフトは暖かい空気が上昇する性質上、どうしても熱がこもりやすい空間です。夏場は「暑すぎてロフトが使えない」という声が多く、エアコンの冷気が届きにくいため電気代がかさむ原因にもなりがちです。
| 対策
・高気密・高断熱の家づくりを大前提とする |
昇降の不便で危険な場合がある
ロフトへの昇降には、はしごや急な階段が使われることが多く、これが日常生活における不便さや危険につながることがあります。「重い物を運べず、結局ロフトを十分に活用できていない」といった後悔や、小さなお子さんや高齢の方がいる家庭では「転落の危険性がある」といった不安を感じることも少なくありません。
| 対策
・勾配の緩やかな固定階段の設置を検討する(※地域によっては、ロフトへのアクセス方法に制限がある場合があるため、事前に確認が必要です。) |

プライバシーの確保がしにくい
ロフトは開放的な空間であるため、視線や音が気になるというデメリットがあります。例えば、「ロフトに収納したものが下の部屋から丸見えで気になる」「下の階の音が気になってロフトで集中できない」といった不満や、来客時にロフトが使いづらいと感じることもあるでしょう。
| 対策
・ロールスクリーンや可動間仕切りを設置し、必要に応じて空間を仕切れるようにする |
掃除に手間がかかる
高い位置にあるロフトは、掃除がしにくいと感じることも多いようです。「ホコリが溜まりやすいのに、掃除が億劫でついつい放置してしまう」といった後悔の声も聞かれます。
| 対策
・コンパクトで扱いやすい掃除用品を活用する |
ロフトのある家のメリット

前項で挙げたようなデメリットがある一方で、ロフトには多くの魅力があります。
空間を有効活用できる
限られた床面積でも天井の高さを利用して新たなスペースを生み出すことができるため、空間を有効活用できます。通常の居住空間を確保しつつ、収納・作業スペースなど多目的に利用可能です。
また、吹き抜けと組み合わせることで、実際の広さ以上の開放感を演出し、明るく伸びやかな住まいを実現できます。
秘密基地のようなワクワク感がある
ロフトは、家の中にいながら特別な雰囲気を感じさせる場所です。読書や趣味の時間を過ごすのに最適なプライベート空間であり、隠れ家的な雰囲気を楽しめます 。子どもにとっては秘密基地、大人にとっては非日常的なリラックス空間となり、自分だけの特別な空間を作り上げることができます。
家族のつながりが深まる
吹き抜けを通して階下のLDKと緩やかにつながるため、家族の気配を感じやすく、自然なコミュニケーションが生まれる温かい住まいになります。
ロフトに設置するのは、階段とはしごどっちがおすすめ?
ロフトへのアクセス方法は、主に「はしご」と「階段」の2種類があり、それぞれの特徴を理解し、利用目的に合わせて選択することが重要です。
はしごのメリット・デメリット
ロフトにはしごを設置するメリット・デメリットについては、以下の表をご覧ください。
| メリット
・省スペースで設置できる |
デメリット
・昇り降りが急で不安定になりがち |
階段のメリット・デメリット
ロフトに階段を設置するメリット・デメリットについては、以下の表をご覧ください。
| メリット
・昇降が安定している |
デメリット
・広い設置スペースが必要 |
どちらを選ぶべきか
ロフトを頻繁に利用する予定がある場合や、安全性・利便性を重視するなら「階段」がおすすめです。ロフトを寝室や子ども部屋、書斎など、日常的に使う空間として考えている場合は、階段の方が快適に利用できるでしょう。
ロフトを主に収納スペースとして利用する場合や、部屋のスペースを最大限に活用したい場合は「はしご」も選択肢となります 。ただし、昇降時の安全性には十分な配慮が必要です。手すり付きのはしごを選ぶなど、安全対策を講じることも検討しましょう 。
最終的には、ロフトの使用目的、家族構成、部屋の広さ、そして地域の建築基準などを総合的に考慮し、最適な昇降方法を選ぶことが大切です。
ロフトの賢い活用方法
ロフトは多様な使い方が可能です。家族構成やライフスタイルに合わせたアイデアで、空間を最大限に活かしましょう。
第二のリビング・書斎
静かに読書や集中して作業ができる「こもり感」のある空間に。天井の高さに合わせたローテーブルや座椅子を選ぶと良いでしょう 。

趣味の部屋
ホームシアター、コレクション展示、楽器の練習、手芸や模型作りの作業場など、趣味に没頭できる場所に。趣味に合わせた照明やインテリアで、特別な雰囲気を演出できます。
子どもの遊び場・学習スペース
子どもにとって自分だけの特別な空間で、想像力を育む場、集中できる学習の場に。子どもの成長に合わせてレイアウトが変更できるようにしておくと便利です。

ゲストルーム
来客時に便利な予備の寝室としても活用できます。その場合には、プライバシーを確保できるようにしましょう。
大容量収納
季節家電やレジャー用品など、普段使わないものの収納に役立ちます。収納ボックスや引き出しを活用することで、狭い空間でも整理整頓しやすくなり、他の生活空間を広く保てます。
ロフトを設ける上でのポイント
理想のロフトを実現するためのポイントをご紹介します。
使い勝手のシミュレーションを行う
実際に何に使うか、家具の搬入経路、昇降のしやすさ、コンセントや照明の位置までを具体的にイメージし、細部まで計画することで、後悔のないロフトになります。
将来を見据えて計画する
現在だけでなく、将来的な家族構成の変化や加齢による体の変化も考慮に入れ、フレキシブルに対応できる設計を心がけましょう。
実績が豊富な設計士に相談する
ロフトには建築基準法上の厳しい制約がありますので、法的知識はもちろん、快適性やデザイン、使い勝手に関するノウハウを持った設計士に相談し、アドバイスをもらうことが重要です。
まとめ

今回は、家にロフトを設けるメリット・デメリット、そしてその活用方法等について詳しくご紹介しました。ロフトは空間を有効活用できる一方で、暑さや転落といったリスクも伴います。こうしたリスクを軽減し、安全かつ快適にロフトを利用するためには、はしご選びが大切です。
ウッドワンのロフト用はしごは、木製やアルミ製など豊富なバリエーションがあり、デザイン性と機能性の両方を兼ね備えています。手すり付きのモデルや各タイプの高さに対応した商品が用意されており、家庭の状況に合わせて選べます。安全性はもちろん、シンプルで美しいデザインが特徴です。ロフト設置をお考えの方は、ウッドワンのはしごで、快適で安全な空間づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
RELATED
関連する記事

WOODONEマガジンは"地球と人に価値ある木の空間を"をテーマに暮らしに役立つ情報を配信しています。