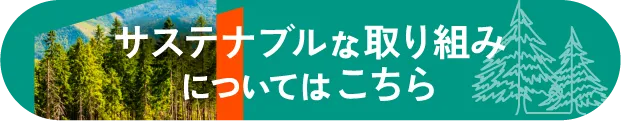人材採用(新卒・中途採用)に関するメディア、会社案内・入社案内、PR誌、社内報・会報などの編集・原稿制作を手がけています。また、現在はボランティアなどの市民活動に関するジャンルの取材・情報誌の編集を中心に携わっています。
人材採用(新卒・中途採用)に関するメディア、会社案内・入社案内、PR誌、社内報・会報などの編集・原稿制作を手がけています。また、現在はボランティアなどの市民活動に関するジャンルの取材・情報誌の編集を中心に携わっています。
目次

建築業界では、深刻な人手不足の問題を抱えています。
厚生労働省のデータによれば、2023年2月分の一般職業紹介状況全体での有効求人倍率は1.34倍。これに対し、建設業(採掘含む)は5.34倍となっています。
これは他の産業に比べても非常に高く、業界の将来に影響を及ぼす問題として早急な対策が求められているのです。
今回は、建築業界をめぐる人材の現状と将来について取り上げていきます。
建築業界の人手不足の原因とは

建築業界の人手不足には、大きく分けて3つの原因があります。それを順番に見ていきましょう。
1. 少子高齢化による労働力人口の減少
建築業界の労働力人口の年齢構成は高齢者の割合が高く、若年層の割合が低くなっています。国土交通省の『最近の建設業を巡る状況について』を元に見てみましょう。
これによれば、令和5年の統計では、55歳以上の就業者が全産業では31.5%であるのに対し、建設業では35.9%、29歳以下の就業者が全産業では16.4%であるのに対し、建設業では11.7%です。
現状で高齢者の割合が高くなっていることに加え、55歳以上の人材が今後10年程度をめどに退職していくことを考えると、若い人材の獲得は業界の将来を左右します。
しかし、少子高齢化により労働力人口そのものが減少していく中、建築業界もその影響を受け、職人不足や大工不足、さらに技術の承継といった問題に直面しているのです。
2. 労働環境問題
次に、労働環境問題が挙げられます。建築業界は「きつい・汚い・危険」のいわゆる「3K」の代表格のようにいわれてきました。
工期に追われ、長時間労働を強いられる過酷な仕事であるにも関わらず低賃金というイメージが強く、若い人材から敬遠されがちな傾向にあります。
たとえば厚生労働省『毎月勤労統計調査』による年間の総実労働時間を見ると、建設業は全産業と比べて90時間長いという結果に。また、20年程前と比べると、全産業では労働時間が約90時間減少していますが、建設業は約50時間減少と小さい減少幅にとどまっています。
建設業における休日の状況では、4週6休以上が全体の6割以上となっていますが、1割以上が4週4休程度以下という現状です。
就業率の低さに加え、離職率の高さも同じところに原因があると見られます。
3. 建設業の需要の拡大
建設業の需要が拡大している点も、人手不足に拍車をかけています。
日本の建設投資額(政府+民間)は、平成4年度の約84兆円をピークに、平成23年度には約42兆円まで落ち込みました。しかしその後、増加に転じて令和5年度は約70兆3,200億円の見込みとなっています。
一方、建設業者数(令和4年度末)は約47万5,000万業者で、建設業就業者数(令和4年平均)は479万人と、平成23年度からほぼ横ばいの状態が続いており、需要の拡大に追いついていないのが現状です。
【出典】国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」
建築業界の人手不足を改善するには

では、こうした状況を改善するためにはどんな対策が必要なのでしょうか。
建設業界では、公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律をまとめた「担い手3法」があり、これを改正した「新・担い手3法」が令和元年に成立しました。
この中で建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定し、課題に取り組んでいこうとしています。
その主なポイントを挙げてみましょう。
1. 働き方改革による労働環境の整備
建設業界での働き方改革は、「長時間労働の是正」「工期の確保や施工時期の平準化」「処遇改善」などが柱となっています。
発注者の責務として、休日や準備期間などを考慮した工期設定などが求められるのに対し、受注者側としても適正な請負代金・工期での下請契約の締結が責務とされています。
また、「建設キャリアアップシステム」という官民一体となって普及を促進している制度があります。
これは、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価されることで、技能者の適切な処遇につなげる仕組みです。
これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、③技能者を雇用し育成する企業が伸びていける、という建設業全体の改革を目指すものです。
2. 適正な工期設定
特に重要なポイントとされる工期の設定については、中央建設業審議会が工期に関する基準を作成し、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期による請負契約の締結を禁止。
また、建設業の働き方改革のための関係省庁連絡会議において「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定し、関係省庁に要請するなどの取り組みを行っています。
3. 生産性の向上
生産性の向上については、人材の雇用以外の対策も併せて考える必要があるでしょう。
省施工製品の導入による工数の効率化やICTやAI技術の活用、ロボットの導入による省人化など、先端技術を取り入れていくことで生産性と働きやすさを確保する方向性が打ち出されています。
ただ、これらは短期間に実現できるものばかりではありません。大手企業がリードしながら進めるべき施策もありますが、中堅・中小企業もできるところから取り組んでいくことが、業界全体のイメージアップにもつながっていくでしょう。
ウッドワンが考える大工人数の減少をはじめとする社会課題への取り組み
ウッドワンでは建築業界の人手不足などの問題を踏まえ、製品やシステムの開発に取り組んでいます。
将来の職人の減少を見据え、省施工商品の開発や構造設計を見直すことで、労務工数を効率化する省施工システムの研究・提案を行ってきました。
省施工商品の一例としては、製造段階でほぼ全ての部材にプレカットを施した「ジャストカット階段」や、「丸棒手摺ジャストカットシステム」などの商品・サービスを展開。これらの商品は現場でカットの必要がなく、作業効率の向上と品質の均一性が保たれるメリットがあります。
ほかにも多数の省施工商品を開発しており、「省施工カタログ」でご覧いただくことができます。
省施工システムでは、設計段階から見直しを行うことで、労務工数の効率化を実現できるオリジナルの内装省施工システムを提案しています。
そのポイントは、収納部を中心に“柱配置を変える”「プチスケルトン構造」の採用。これにより現場での部材カット回数を減らし、労務工数を効率化できます。これは、工場と構造設計部門を社内に持つウッドワンならではの提案です。
ウッドワンでは、これからもこうした活動を通して、社会課題の解決に貢献していきます。
詳しくは「ウッドワン サステナビリティレポート」でご覧ください。
RELATED
関連する記事

WOODONEマガジンは"地球と人に価値ある木の空間を"をテーマに暮らしに役立つ情報を配信しています。