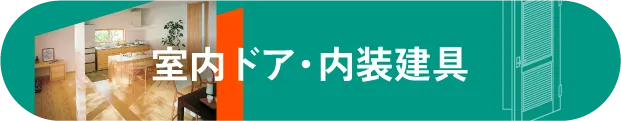「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
目次

家づくりやリフォームを始めると、普段はあまり聞きなれない言葉に出会うことがあります。
そのひとつが「建具」です。なんとなく扉のことかしらと思いつつ、正確にはよくわからない…そんな経験はありませんか?
建具は、家の快適さやデザインを左右する非常に重要な要素です。この記事では、建具の基礎知識から種類・素材の違い、そして後悔しない選び方のポイントまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
建具とは

建具(たてぐ)とは、戸・障子・ふすまなど゙開閉して部屋を仕切るもの”の総称です。簡単にいうと、扉や窓を指す建築用語です。建具があることで、出入り・採光・通風・プライバシーの確保ができます。
建具には大きく分けて「外部建具」と「内部建具」の2種類があるので、以下で解説します。
外部建具
外部建具とは屋外と室内を隔てるための建具で、主に玄関ドア・窓・勝手口などを指します。
防犯性・断熱性・耐風圧性など多くの性能が求められ、後悔しないものを選ぶのが難しい要素です。
たとえば、断熱性のないドアを選ぶと冬には冷気が室内に入り込み、室温が2〜3℃下がることがあります。防犯性能が低いと、空き巣にわずか30秒程度で侵入されるというデータも。
耐久性のあるアルミや複合材、ディンプルキーなどで対策すると安心です。
内部建具
内部建具は家の中を仕切るもので、室内ドア・引き戸・障子・襖・間仕切りなどを指します。音や光の遮断、動線の確保などのために建具をつけます。
たとえば寝室とリビングの間に建具がないと、リビングでの会話やテレビの音が寝室まで響いてしまい、眠れない原因になりかねません。逆にキッチンからダイニングに続く通路に開き戸を設置すると、料理を運ぶときに開閉が面倒でストレスが溜まる原因に。
デザイン性も大切ですが、このように設置場所に応じた機能性を考えることが、快適な暮らしの鍵となります。
建具の素材

建具は、使う素材によって性能や見た目、使い勝手が大きく変わってきます。ここでは木・アルミ・鉄の建具について、特徴を紹介します。
木
木は湿気を吸ったり吐いたりする性質があり、日本の気候にぴったりな素材です。昔から障子や襖、室内ドアなどに多く使われ、和室には欠かせない素材として活躍してきました。手触りや風合いに個性が出やすく、使うほどに風合いが増し、経年変化を楽しめます。
ただし、木は水に弱いので外に取り付けるにはあまり向きません。どうしても玄関の扉を木にしたいときは、雨除けをつけるなど工夫しましょう。
アルミ
アルミ製は軽くてサビにくく丈夫なので、主に外で多く使われています。特に玄関ドアや掃き出し窓などに使われることが多く、最近はカラーバリエーションやデザイン性も豊富なので、おしゃれさを重視したい方にも選ばれています。
ただし、単体のアルミは断熱性がやや低いため、寒い地域では樹脂や木と合わせたタイプが好まれることも。他の素材と合わせて性能をアップできるのも、取り入れやすさにつながっています。
鉄
鉄製の建具は強度があるうえに火にも強いので、商業ビル・マンションの玄関・学校・病院の出入口にもよく使われます。頑丈さや防犯性が求められる場所で重宝されます。
ただし、サビやすいという弱点があるため、外に設置する場合は防錆処理や塗装が欠かせません。
建具の種類と特徴

ここからは建具の特徴や使い分け方を紹介します。今回紹介するのは次の3つです。
・最も一般的なスタイルの開き戸
・場所を取らない引き戸
・収納や水回りで活躍する折れ戸
最も一般的なスタイルの開き戸
開き戸とは、丁番(ちょうばん)を使って弧を描くように開閉するように作られた建具です。構造がシンプルでコストを抑えやすいのが特徴です。
気密性・遮音性に優れていて冷暖房効率も高いので、過ごしやすい部屋を作りやすいのがメリットです。デザインや取っ手のバリエーションも豊富で、部屋の雰囲気に合わせやすい点も魅力です。
ただし、開閉に扇形のスペースが必要なため、家具の配置を間違えると一気に使いにくくなります。
場所を取らない引き戸
引き戸は、ドアを横にスライドさせて開閉するタイプの建具です。開閉のためのスペースが不要なため、廊下や限られた空間にも設置しやすい扉です。
戸を開けたままでも邪魔にならないため、開け放ったまま2部屋を1つの空間にする、という使い方もできます。高齢者や車椅子利用者にも開閉しやすいため、バリアフリー住宅にも多く採用されています。
気密性・遮音性がやや劣ることと、下にレールがある引き戸は滑走音や掃除のしづらさが気になる人もいる点がデメリットです。
収納や水回りで活躍する折れ戸
折れ戸はパネルが中央で折りたたまれる構造で、クローゼットや洗面所の仕切りなどによく使われます。あまり場所を取らずに、開口部を大きく取れるのが最大の特徴です。扉を開け放てば中に何が入っているか見やすく、出し入れも簡単。
ただし、折りたたみ部分の厚みによっては若干のデッドスペースができたり、お子さんが指を挟んだりする恐れがある点が要注意です。
建具の選び方

最後に、建具を選ぶ際に失敗しないためのポイントをお伝えします。
・生活動線を考えて選ぶ
・部屋の雰囲気と合わせて選ぶ
・手入れのしやすさで選ぶ
最低限、以上の3点は押さえておきましょう。
生活動線を考えて選ぶ
建具を選ぶときは、家の中での動き=生活動線を必ず考えましょう。「どこで・誰が・どんなふうに使うのか」を想像しながら選ぶことで、日常のストレスを減らせます。
たとえば狭い廊下に開き戸をつけると扉を開け閉めするときに人とぶつかる可能性が高くなります。お子さんが片付けで使う戸棚に折れ戸をつけると、指を挟んでケガをするかもしれません。
どのように使うのか考えて建具を選ぶことで、後悔しにくい家づくりができます。
部屋の雰囲気と合わせて選ぶ
建具はインテリアの一部として部屋の印象を大きく左右します。ナチュラルな部屋には木目調、モダンな空間にはブラックフレームのアルミなど、統一感が大切です。
壁紙や床材と建具の色が合っていないとちぐはぐな印象の家になり、落ち着かない部屋になりがち。見た目も住み心地もよくしたいなら、家具とのバランスも考えて建具を選びましょう。
手入れのしやすさで選ぶ
建具は毎日触れる場所だからこそ、お手入れのしやすさも大切です。
たとえば、引き戸の下にレールがあるタイプはホコリが溜まりやすく、掃除機でも取りにくいもの。上吊り式の建具にすれば、床にレールがないため掃除がラクです。
扱いやすさを基準に選ぶと、家を清潔に保ちやすくなるのでおすすめです。
まとめ

今回は建具とは何かについて、基礎知識から後悔しない選び方まで紹介しました。建具は単なる扉や仕切りではなく、家の使いやすさ・快適さ・デザイン性を大きく左右するものです。動線・雰囲気・手入れのしやすさといった、生活に直結する視点も欠かせません。
数ある建具の中でも、特に木の温もりや質感を大切にしたい方におすすめなのが、ウッドワンの「ピノアースシリーズ」です。無垢の木材を贅沢に使用したこのシリーズは、ナチュラルな木目が見た目にもやさしい温もりを与えてくれます。
デザインも質感も豊富でどんな家にも取り入れやすいので、これから建てる家の建具を探している方は、ぜひ候補に加えてみてください。
RELATED
関連する記事