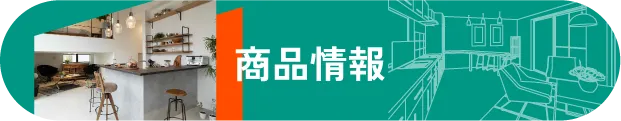「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
目次

空気を整え、湿度を調節し、そこにいる人の呼吸や気持ちまで静かに整えてくれる。そんな木の性質に惹かれて、いま“木造建築”を選ぶ人が増えています。
ただ「音が響くんじゃない?」「耐久性に不安があるかも」といった心配の声も。
そこでこの記事では、木造建築のメリットとデメリット、そしてその建て方の違いについて、わかりやすくご紹介します。ぜひ参考にしてください。
木造建築のメリット

木造建築は見た目のやさしさだけではなく、暮らしやすさや経済性の観点からも、家づくりを考える多くの人に選ばれている構造です。ここでは木造の5つのメリットを詳しく解説していきます。
- ・建築コストが抑えられる
- ・年中湿度を一定に保てる
- ・耐火性がある
- ・リラックス効果が期待できる
- ・環境にやさしい
-
建築コストが抑えられる
- 木造建築は他の構造と比べて、建築費用が安くなります。 木材自体が鉄骨やコンクリートよりも安価で、基礎工事や運搬のコストも低く抑えられるからです。
- 一般的な30坪の戸建て住宅を木造で建てた場合、鉄骨造よりも200〜400万円ほど安く済むことがあります。工期も短いため、仮住まいや人件費も削減可能です。コストを抑えながら理想の住まいを建てたい方にとって、木造は有力な選択肢となるでしょう。
-
年中湿度を一定に保てる
- 木造建築なら、1年中快適な湿度を保ち続けられます。木が空気中の水分を吸ったり吐いたりしてくれる「吸放湿性(きゅうほうしつせい)」という性質を持っているからです。
- 梅雨時でも室内がジメジメせず、冬場の乾燥も和らげてくれます。エアコンに頼りすぎず快適に暮らせるので、健康にも電気代にもやさしい暮らしができます。
-
耐火性がある
- 「木は燃えやすい」という印象がありますが、実は木造は一定の耐火性能を持ちます。木は燃え始めると表面が炭化し、その炭の層が内部への燃焼を遅らせるためです。 火事が起きても、建物全体の崩壊を防ぐ「延焼防止効果」が期待できます。
- 国土交通省の基準でも、準耐火・耐火構造として認定された木造建築が多数あります。適切な設計で断熱材・石膏ボードを使って建てれば、鉄骨に匹敵する安全性を確保できるでしょう。
-
リラックス効果が期待できる
- 木造住宅は、住む人の心と体にやさしい「リラックス効果」をもたらします。木の香りに含まれる「フィトンチッド」という成分には、自律神経を安定させる効果があるのです。 森林浴で感じるあのすがすがしさを日常生活にも取り込みたい方にぴったりです。
-
環境にやさしい
- 木材は、樹木として成長する過程でCO₂を吸収して炭素として蓄えます。伐採された後も、この炭素は木材の中に固定されたまま残り続けます。
- つまり、建材として使われている間も、木材の中には大気中から取り込まれた炭素が貯蔵され続けているため、CO₂の削減に貢献しているのです。「環境に配慮した家づくり」をしたい人にとって、木の家は理想といえるでしょう。
- 以下のページでは、ニュージーランドの森で1本の苗木を植えるところから始まる、ウッドワンのものづくりの物語を紹介しています。木材にもこだわって家づくりをしたい方は、ぜひ目を通してみてください。
- □THE WOODONE QUALITYをみる
-
木造建築のデメリット

- 木造建築には多くの魅力がありますが、当然ながらデメリットも存在します。
- ・耐用年数が短め
- ・シロアリや腐れに弱い
- ・防音性が低い
- 構造の性質上避けられない部分もあるので、これらをしっかり把握した上で選ぶことが大切です。
-
耐用年数が短め
- 木造建築は鉄骨や鉄筋コンクリートと比べて、耐用年数が短い傾向があります。木材が湿気や腐食に弱く、劣化が早まりやすいからです。国税庁が定める法定耐用年数では、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年とされています。 しかし、これはあくまで税法上の資産価値を計算するための数字であり、実際の建物の寿命を示すものではありません。
- 適切なメンテナンスを行えば、日本の木造住宅は30年、50年、さらには100年と長持ちさせることが可能です。ただし、鉄骨造などに比べて湿気や腐食への対策が重要になるため、長期的な修繕計画を立てておくことが大切です。
-
シロアリや腐れに弱い
- 木造住宅は、シロアリなどの被害を受けやすい弱点があります。特に床下や柱の土台部分は湿気がこもりやすく、シロアリの住処になりがちです。 住宅金融支援機構の調査では、中古木造住宅の約15%にシロアリ被害の痕跡が見つかっています。シロアリが発生すると目に見えない部分から構造が侵され、最悪の場合、耐震性が著しく低下することも。 そこでおすすめしたいのが「JWOOD EX」という特別な構造材です。
- 通常の木造住宅では、現場で薬剤を表面に塗るだけの処理が多く、10年ほどで効果が薄れてしまうこともあります。しかし、この木材はシロアリや腐れを防ぐ薬剤を、表面だけでなく内部の芯までしっかりと圧力をかけて染み込ませる「乾式加圧注入方式」という方法で処理されています。薬剤が長期間にわたって木材内部にとどまり続けることで、シロアリや腐朽への耐性が半永久的に保たれます。
- シロアリや腐れに弱いという弱点を対策したい方は、乾式注入材JWOOD EXを検討してみてください。
- □JWOOD工法をみる
-
防音性が低い
- 木造は鉄骨やRCに比べて音を通しやすく、防音性が低いといわれています。 これは木材が軽く、音を反射・遮断する力が比較的弱いためです。
- 実際に、「隣の部屋のテレビの音が聞こえる」「2階の足音が響く」などの悩みはよく聞かれます。 防音材の使用や二重サッシ、床の構造改善などで対策は可能ですが、事前に音の問題が起きやすいことを知っておいてください。
-
木造建築の3つの工法

- 木造建築には複数の工法があります。ここでは以下の代表的な3つの工法を解説します。
- ・木造軸組(在来工法)
- ・木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)
- ・木造ラーメン工法
-
木造軸組(在来工法)
- 日本の木造住宅で最も多く使われているのが、木造軸組工法という建築方法です。柱と梁を組み合わせて建物の骨組みを作る「軸組」という仕組みで建物を支えており、日本に古くから伝わる大工の技術が活かされています。
- この工法の大きな特徴は、壁の位置を比較的自由に決められることです。住む人の希望に合わせて間取りを柔軟に設計でき、将来家族構成が変わった時のリフォームにも対応しやすくなっています。
- ただし、構造が複雑になりがちなため、建物の品質が施工する大工の技術力に左右されやすいという側面もあります。それでも現在建てられている木造住宅の約8割がこの工法を採用しています。日本の気候・文化に適した、長年の実績に裏打ちされた建築方法といえるでしょう。
-
木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)
- 木造枠組壁工法は、ツーバイフォー(2×4)材を使って、壁で構造を支える工法です。 北米発祥で、日本でも1970年代以降に広まりました。 壁・床・天井が一体の構造となるため、地震や台風など外からの力に強く、気密性・断熱性にも優れています。工場でパネルを生産するため施工が速く、建築コストが比較的安価に抑えられます。
- 一方で、間取り変更やリフォームには制約が出やすく、開口部(窓・ドア)の設計も自由度がやや低めです。 設計の自由度よりも性能や効率を重視したい方に適した工法といえるでしょう。
-
木造ラーメン工法
- 木造ラーメン工法は、柱と梁をしっかりと固定して接合し、その枠組み全体で建物を支える構造です。「ラーメン」という名前はドイツ語で「枠」を意味する言葉から来ていて、食べ物のラーメンとは関係がありません。
- この工法のメリットは、少ない柱でも高い強度を保てることです。リビングに大きな開口部を作りたい場合や、1階を店舗、2階を住居にするような用途の異なる空間が必要な建物に特に適しています。
- ただし、この工法は高度な技術が必要なため、施工できる建築業者が限られており、建築費用もやや高くなる傾向があります。
-
まとめ

- 今回は、木造建築を建てることを検討している方に向けて、建てる前に知っておきたいメリット・デメリットと工法を解説しました。自然のリズムの中で育った木は、建材になってからも、空間の温度や湿度、人の心にそっと働きかけてくれます。
- そうした“木の旅”にまで意識を向けたものづくりが、ウッドワンにはあります。ウッドワンでは、木の家の骨格となる構造材からこだわったJWOOD工法の家「ONE’S CUBO」をご提案しています。強い構造で安心・安全な木の家を実現したい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
- □構造材 JWOOD[住宅]をみる
RELATED
関連する記事