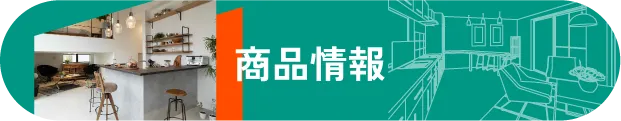「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
目次

大阪・関西万博のシンボル、大屋根リング。世界最大級の木造建築としてギネス世界記録にも認定されたこの巨大な輪は、幅約30m・高さ最大20m・全長2kmにも及ぶ圧倒的スケールを誇ります。しかし、どうやって建てられたのか、どんな工夫が隠されているのかは意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建築に詳しくない人でもわかるように大屋根リングについて丁寧に解説します。ぜひ最後まで目を通してみてください。
ギネス認定も!大屋根リングの構造

大屋根リングは大阪・関西万博会場のシンボルとなる建築物です。大きな輪の形にすることで「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表しています。リング内には世界各国のパビリオンが入っていて「世界がつながる」というメッセージを強く伝える象徴的な存在となっています。
2025年3月4日には「最大の木造建築物」としてギネス世界記録に認定されました。日本の伝統的木造工法を活かしながら、現代の技術で安全性と耐久性を備えた作りになっています。
どれくらい大きい?数字で見るスケール
大屋根リングのスペックは次のとおりです。
| 内径 | 約615m |
| 外径 | 約675m |
| 幅 | 約30m |
| 高さ | 最大約20m |
| 全長 | 約2km |
| 延床面積 | 61,035.55㎡ |
全長は約2km、延床面積は61,035.55㎡、例えるなら東京ドーム約1.3個分の大きさです。109個の木架構ユニットをつないで形づくられた巨大な輪は、会場を囲む空中回廊(スカイウォーク)として機能します。回廊を歩けば視界いっぱいに木の梁と曲線が広がり、まるで空に浮かぶ巨大な散歩道のような感覚を味わえます。
伝統の「貫接合(ぬきせつごう)」
大屋根リングで採用されている貫接合(ぬきせつごう)という工法は、日本の木造建築で古くから使われてきた柱と梁の組み方です。柱に穴を開け、横木(梁や貫材)を通して楔(くさび)で固定します。積み木のブロックを差し込んで、ピタッとはめるようなイメージです。こうすれば、釘や接着剤を使わずに部材を噛み合わせられます。木材の伸縮や揺れに柔軟に対応できるため、地震や経年変化にも強い特徴があります。
「貫接合」を現代仕様にアップデート
大屋根リングに伝統の貫接合をそのまま使うと、現代の耐震基準には届きません。大地震がきたときに楔が梁に食い込み、接合部が緩む恐れがあるためです。
そこで設計チームは接合部に鉄板とボルトを組み込み、木材を金属で挟み込むように補強しました。この工夫によって、接合部のぐらつきにくさが従来の約5倍に向上しました。簡単に言えば、机の脚をネジでしっかり固定すると揺れに強くなるのと同じ原理です。金属は外から見えない位置に隠し、景観の美しさを損なわないよう細部まで配慮しています。
3社協働で進めた建設の裏側
大屋根リングの建設は、竹中工務店・大林組・清水建設が工区を分担し、協力して進められました。
最大の工夫は「ユニット化」です。これは柱と梁をあらかじめ地上で組み合わせてひとつの「部品=ユニット」にし、それをクレーンで所定の位置に持ち上げて取り付ける方法です。従来のように高所で部材を一本ずつ組む必要がないため、作業員の安全性が格段に高まりました。さらに工期の短縮や作業を正確に行うことにもつながり、大規模建築でも効率的に工事を進められました。
構造だけじゃない!見て歩いて楽しい大屋根リング

大屋根リングは巨大な木造建築としての構造美だけでなく、歩いて楽しめる回廊としての魅力も持っています。円形の形は会場全体をひとつにつなぎ、訪れる人を自然に巡らせる効果があります。さらに国産材を多く使った木の温もりや歩くたびに変化する景色、屋上に隠されたメッセージなど、体験することで初めて気づく仕掛けが満載です。ここからは、その見どころを詳しく紹介します。
なぜ「大きな輪」なのか
大屋根リングが円形になった理由は、会場全体を「ひとつのつながり」として体感できるようにするためです。大阪・関西万博のテーマである「多様でありながら、ひとつ」を形にし、中央広場と外周を視覚的にも物理的にも結びました。輪の上を歩けば自然と会場を一周できます。どこからでも景色が開けているので、開放感を味わえます。
木材は国産材70%
大屋根リングに使われた木材の量は約27,000㎥、25mプールおよそ70杯分に相当します。そのうち約7割が国産材で、柱材には四国産ヒノキを約50%、梁材には福島産スギを100%使用。残りの3割は欧州アカマツです。
国産材を積極的に活用することで、地域資源を生かしながら環境負荷を抑えたいというメッセージを発信できています。
歩くだけで発見があるリングの楽しみ方
大屋根リングは単調な道ではなく分岐や高低差があり、歩いていくと少しずつ景色が変わる作りになっています。道の途中には芝生広場や花々が広がり、外向きのルートでは港やパビリオンの屋上を一望できます。上から見ることを想定してパビリオンを作っているので、たとえばセルビア館の屋上には「セルビアはあなたの次のEXPOの目的地です」と大きな文字が。
リングの下をくぐるルートでは、上を歩くのとはまた違った迫力があります。歩くのが苦手な方のために外周バスもあるので、どんな方でも楽しめます。
閉幕したら大屋根リングはどうなるのか

「撤去予定」から「レガシー保存」への転換
当初の計画では、パビリオンと同じく閉幕後に全て解体・撤去される予定でした。
しかし、この圧倒的な規模と、世界最大の木造建築物という技術的、象徴的な価値から、「万博の記憶と理念を後世に伝えるレガシー(遺産)として残すべきだ」という強い声が、地元や関係者から高まりました。
こうした議論の結果、万博協会と大阪府・市などは、大屋根リングを一部保存する方針を固めました。
未来の夢洲に残る「約200m」のランドマーク
未来の夢洲(ゆめしま)のシンボルに保存されるのは、全長2kmのうち約1割にあたるおよそ200m程度の区画です。この部分は、万博の象徴を現地に残すランドマークとして活用される見込みで、来場者が上がって歩ける状態での保存が検討されています。
この決定は、単に大きな建造物を残すという以上の意味を持っています。万博のテーマである「いのち輝く未来社会」の願いを体現したこのリングを、開発が進む未来の夢洲(ゆめしま)における象徴的な存在とし、万博の記憶を未来永劫語り継ぐための、重要な一歩なのです。
課題を乗り越え、新しい時代のシンボルへ
もちろん、巨大な木造建築をレガシーとして残すためには、大きな課題が伴います。
最大の課題は、その維持管理費用です。木材は経年劣化するため、長期的に安全な状態を保つための改修やメンテナンスには、多大なコストと手間がかかります。また、保存する区画の具体的な場所や、将来的な利用方法についても、引き続き検討が進められています。
しかし、かつて1970年の大阪万博で「撤去予定」だった太陽の塔が、今や大阪の不朽のシンボルとして愛されているように、この大屋根リングもまた、課題を乗り越え、新しい時代のシンボルとなる可能性を秘めています。
日本の伝統と技術が結集した巨大な木の輪は、単なる建築物ではなく、万博の感動と「多様でありながら、ひとつ」という普遍的なメッセージを未来へつなぐ、生きたレガシーとなるでしょう。
まとめ

今回は、建築に詳しくない方でも理解できるように、大屋根リングについて解説しました。伝統工法と最新技術を融合した世界最大の木造建築は、木の強さと可能性を改めて示してくれました。
こうした木造建築の知恵は、万博のためだけのものではなく、実は私たちの暮らしにもつながってきます。万博を通じて各社の技術力を高めることで、日本の建築技術が向上するからです。
多くの方が住宅に求めるのは、長く安心して住める強さと安定性でしょう。そんな方におすすめしたいのが、品質のバラつきの少ない強靭な構造用LVL「JWOOD」を専用金物で緊結した、強固な構造体「JWOOD工法」です。繰り返しの地震に強く、建てた当初の性能をしっかりと維持できるので、長く安心して住み続けられる家を建てたい方におすすめです。
詳細は次のページにて解説しておりますので、ぜひご覧ください。
RELATED
関連する記事