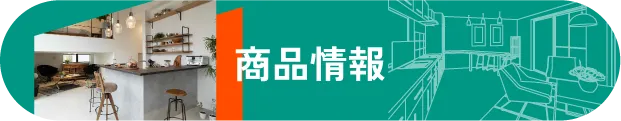「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
「木のぬくもりを暮らしの中へ」をテーマにキッチン、建具、床等の住宅部材をトータルでご提案する(株)ウッドワン。 編集部では、皆さまが快適な家づくりをするための役立つ情報や、楽しいコンテンツを日々こつこつ集めて発信してきます。
目次

家を建てるなら、できるだけ長く快適に住み続けたいものです。しかし、日本の住宅は平均寿命が短く、建て替えのコストや環境負荷がかかる問題点が…。そんな中、国が推奨する「長期優良住宅」は耐久性や省エネ性に優れ、資産価値を維持しやすい住宅として注目されています。本記事では、長期優良住宅のメリット・デメリットを詳しく解説し、認定を受けるための条件についても分かりやすく紹介します。家づくりを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、国が認めた耐震性や耐久性、メンテナンス性に優れた住宅のことです。一般的な住宅と比較して、厳しい基準をクリアしています。
この制度の目的は住宅の質を高め、環境への負担を抑えつつ資産価値を保つことにあります。また一定の耐震性・耐久性・省エネ性能を満たすことで、住宅ローン減税や固定資産税の優遇措置など、さまざまなメリットを受けられる点も魅力です。
長期優良住宅の基準ができた背景
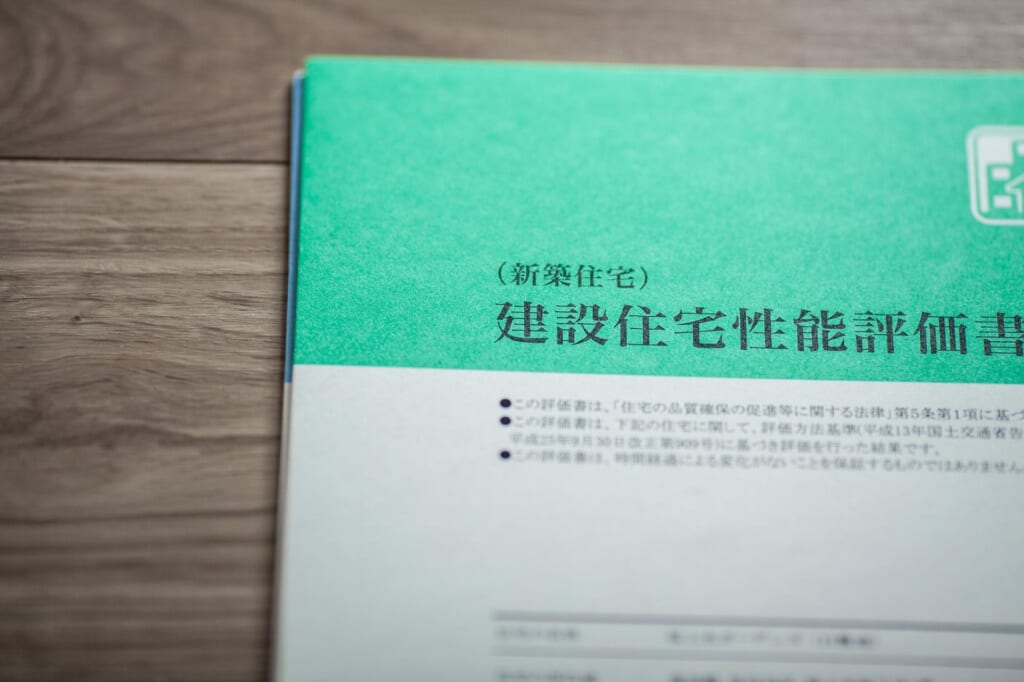
日本では住宅の平均寿命が欧米に比べて短く、建て替えを繰り返すことで資源を無駄使いしたり自然環境に負荷をかけたりしてしまうことが課題となっていました。改善策として2009年に「長期優良住宅認定制度」が導入され、耐震性や省エネ性能に優れた住宅の普及が進んでいます。
この制度により、寿命の短い住宅から適切な手入れをしながら長く住み続けられる住宅へと、暮らしのスタイルが大きく変わりつつあります。
長期優良住宅の認定を受けるメリット

長期優良住宅の認定を受けるメリットとして、次の3つが挙げられます。
- ・住宅ローンの金利が引き下げられる
- ・税の特例措置が拡充される
- ・地震保険料の割引が受けられる
-
住宅ローンの金利が引き下げられる
- 長期優良住宅に認定されると、住宅ローンの金利が優遇される制度を利用できる可能性があります。
- 例えばフラット35で長期優良住宅向けの金利引き下げ制度が適用されれば、通常よりも低い金利でローンを組める場合があります。返済総額も抑えられるため、長期的な資金計画を立てる上でも大きなメリットです。
- 初期投資は一般住宅よりも高くなることが多いですが、低金利の恩恵を受けることで、結果的にコストを抑えられます。
-
税の特例措置が拡充される
- 長期優良住宅に認定されると、税制面での優遇措置を受けられます。具体的には、住宅ローン減税の控除額が一般住宅よりも拡充されたり、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置が適用されたりします。住宅取得・保有期間中の税負担を軽減できるため、長期的な資産形成にも有利です。
- ただし、税制優遇は年ごとに変更される可能性があるため、最新情報の確認を怠らないようにしましょう。
-
地震保険料の割引が受けられる
- 長期優良住宅は耐震性の高い建築基準を満たしているため、地震保険料の割引を受けられます。長期優良住宅は地震に強い構造になっているため、保険会社がリスクを低く見積もってくれるのです。
- 具体的には、耐震等級が2以上であれば30%、等級3であれば50%の割引が適用される場合があります。保険料の節約ができるだけでなく、実際に地震が発生した際の安全性も高いため、安心して住み続けられます。
-
長期優良住宅の認定を受けるデメリット

- メリットの多い長期優良住宅認定制度ですが、以下のとおりデメリットもあります。
- ・申請に時間とお金がかかる
- ・メンテナンスを怠ると認定が取り消される
-
申請に時間とお金がかかる
- 長期優良住宅の認定を受けるためには申請手続きが必要で、そのための費用と時間がかかります。申請には設計図や性能評価の書類を準備する必要があり、専門家に書類を作ってもらうための追加の費用も発生します。
- 自治体によっては審査に時間がかかることもあり、スムーズに認定を受けられないケースも。認定を目指す場合は、早めに準備を進めることが大切です。
-
メンテナンスを怠ると認定が取り消される
- 長期優良住宅の認定を維持するためには、定期的なメンテナンスが求められます。具体的には、劣化対策や設備の点検などを実施し、住宅の性能を維持する必要があります。
- もし適切な維持管理が行われない場合、自治体から認定を取り消される可能性も。認定を取り消されると税制優遇や住宅ローンの優遇措置が受けられなくなります。長期優良住宅を取得した後も、定期的なメンテナンスのコストや手間が発生することを念頭においておきましょう。
-
長期優良住宅の認定を受ける9つの条件

- 長期優良住宅の認定を受けるには、以下の9つの条件を満たす必要があります。
- 1.劣化対策
- 2.耐震性
- 3.維持管理
- 4.省エネルギー性
- 5.居住環境
- 6.住戸面積
- 7.可変性
- 8.バリアフリー性
- 9.長期的な維持保全計画
- なお「可変性」「バリアフリー性」は共同住宅等の認定基準のため、一戸建ての場合は適用されません。
-
1. 劣化対策
- 住宅の基本構造を維持するための劣化対策が求められます。具体的には、木造住宅の場合は床下や屋根裏の換気を確保し、腐朽やシロアリ被害を防ぐ対策が必要です。鉄筋コンクリート造の場合は、劣化しにくい材料を使用するなど、構造の耐久性を向上させることが求められます。
-
2. 耐震
- 長期優良住宅は、地震に強い構造であることが必須です。具体的には、建築基準法で定める耐震性能(震度6強〜7の地震でも倒壊しないレベル)を満たすことに加え、さらに耐震等級3以上を確保することが求められます。
-
3. 維持管理
- 住宅を長く使い続けるために、設備の交換・修繕がしやすい設計であることが求められます。具体的には、配管や設備機器がメンテナンスしやすいように点検口を設ける、配管の交換が容易な設計にするなどの工夫が挙げられます。
-
4. 省エネルギー性
- 環境への配慮と光熱費の削減のために、省エネルギー性能も求められます。断熱材を使ったり高効率な設備を取り入れたりして、建築物省エネルギー性能基準(いわゆる「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6」)を満たす必要があります。
-
5. 居住環境
- 住宅の周辺環境と調和しているかも、長期優良住宅の認定条件の一つです。自治体によっては、地域の景観や環境保全に配慮した設計が求められることがあります。
-
6.住戸面積
- 良好な居住水準を確保するための規模を担保するため、住戸面積の基準もあります。一戸建ての住宅において、75㎡以上(少なくとも1つの階の床面積が 40 ㎡以上)が必要です。共同住宅等の場合は40 ㎡以上とされています。ただし、地域の実情によって所管行政庁が変更することがあるので、ご自身の自治体ホームページなどを確認しましょう。
-
7. 可変性 ※共同住宅の場合
- ライフスタイルの変化に対応できる住宅であることも大切です。ライフステージの変化に応じて間取りを変更できる設計にする、家族構成の変化に合わせて部屋を仕切れるようにするなど、柔軟性が求められます。
-
8. バリアフリー性 ※共同住宅の場合
- 長く使うことを想定して、高齢者や障がい者も安心して住めるように、バリアフリー設計にする必要があります。具体的には段差を極力なくす、廊下やドアの幅を広めに確保するなどの対策が必要です。
-
9. 長期的な維持保全計画
- 長期優良住宅として認定されるためには、維持保全計画の作成が必須です。維持管理を怠ると認定が取り消される可能性があるため、適切なメンテナンスを実施できるような点検・修繕スケジュールを立てましょう。
-
まとめ

- 今回は、長期優良住宅についてメリット・デメリットを踏まえつつ解説しました。安心して長く住み続けられる家を造りたいなら、長期優良住宅認定制度を利用して国のお墨付きを得ると良いでしょう。
- いつもの安心・快適がいつまでも続くために長期優良住宅の基準を満たした高性能な住まいを求めるなら、ウッドワンのワンズキューボを検討してみてはいかがでしょうか。ワンズキューボは耐震性をはじめ、多くの基準で最高等級を獲得し、高いレベルでその性能を満たしています。特に長く住み続けられることを重視しており、ライフステージの変化に応じて間取りを変更できます。手入れをしながら長く大切に使い続けられる家・ワンズキューボについて詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。
- □ウッドワンのワンズキューボをみる
RELATED
関連する記事